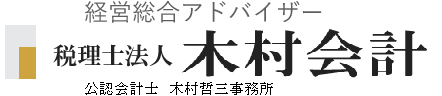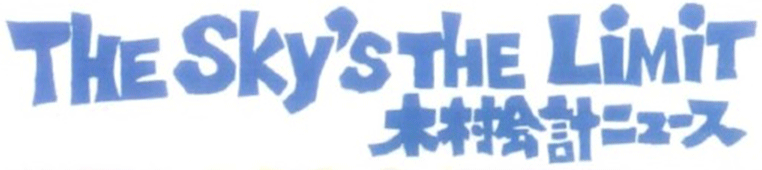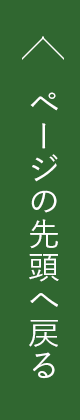賃金のデジタル払い
令和5年(2023年)4月から「労働基準法施行規則 第7条の2」が改正され、一定の要件を満たす場合には賃金をデジタルマネーで支払うことが認められることとなりました。一定の要件とは、
1.指定資金移動業者の決済サービスのみ利用可能
厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者が提供するものに限られます。
指定を受けるための要件とは、
・1円単位で入出金ができること
・現金による残高払い戻しが可能で、かつ毎月最低1回は手数料なしで残高を払い戻せること
・原則として、最後の入出金日から最低10 年間は残高を払い戻せること等のすべてを満たす必要があります。
2025年2月末時点で、PayPay㈱と㈱リクルートMUFGジネスが指定を受けており、楽天Edy㈱と楽天ペイメント㈱が申請済・審査中となっています。
2.労使協定の締結が必要
労働組合又は労働者の過半数代表者と使用者の間で、以下の事項を定めた労使協定を締結する必要があります。
- ・デジタル払いの対象となる労働者の範囲
- ・デジタル払いの対象となる給与の範囲、金額
- ・デジタル払いに用いる決済サービス(指定資金移動業者)の範囲
- ・デジタル払いの実施開始時期
- ・その他必要事項
締結事項については就業規則・給与規程等を改定し、労働基準監督署への届出が必要となります。(常時10名以上の労働者を雇用する使用者が対象)
3.労働者への説明・個別同意が必要
デジタル払いは、労働者の個別同意が必要となります。
指定資金移動業者名称や1.の決済サービス内容等を説明し理解を求めます。個別同意にあたっては、内容説明の実施日、デシタル払いの承諾、開始希望時期、希望金額等を付記した同意書を作成する必要があります。(口頭での確認・同意だけでは足りないことに留意する必要があります)
給与を労働者の指定するデシタルマネーの口座に入金することは、通貨払いの原則に対する例外的な方法に該当することから、労働者の同意を得た場合に限り支払うことが可能となります。なお、使用者からデジタルマネーによる給与支払いを強制するとは出来ません。
4.使用者はデジタル払いに応じる義務はない
大前提として、労働者からデシタル払いを求められても使用者はそれに 応じる義務はありません。労働者は給料の受給方法の選択肢が増える等の メリットがありますが、事務業務量の増加、運用管理コスト等を考慮し、 使用者の判断で現状の給与支払方法を継続することができます。
デジタル払いのメリット
「労働者」
- ・キャッシュレス決済を利用している労働者にとって利便性がある
- ・銀行振り込み、デジタル払いと2つの受給方法(併用可)を利用できる
「使用者」
- ・企業イメージの向上、雇用機会の増加につながる
- ・外国人労働者、日雇労働者等の支払いへの対応がしやすくなる
- ・給与振込時の振込手数料が削減される場合がある
デジタル払いのデメリット
「労働者」
- ・指定された資金移動業者しか利用できない
- ・デシタル払いは口座の残高上限額があり、残高管理が必要となる
- ・資金移動業者の破綻や時効による残高消滅のリスクがある
- ・不正アクセス等のセキュリティ面のリスクがある
「使用者」
- ・労働者の個別対応が必要となり、給与支払業務量が増える
- ・システム構築、運用管理面のコストが発生する
デジタル払いは、雇用する人材の多様化や労働者の利便性等を考慮すれば、今後、利用価値の高い支払方法となる可能性があります。また、新しいことに取り組む企業というイメージから人材不足解消にも役立つ可能性があります。
検討してみてはいかがでしょうか。