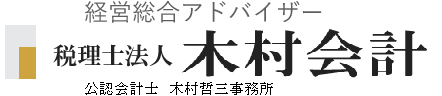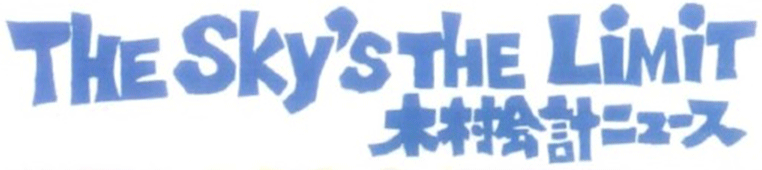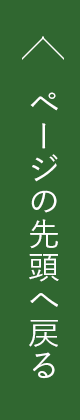「年収の壁」の現状と今後
令和7年度税制改正では、所得税の基礎控除額の引き上げなど身近な税制に変更がありました。これに関連して、いわゆる「年収の壁」との関係について整理してみたいと思います。
〈100万円の壁〉住民税
「100 万円の壁」とは、住民税の所得割が課税される基準となる年収(給与収入)の目安です(均等割の課税は自治体によって異なります)。
令和7 年度の税制改正では住民税に関する直接的な改正はなかったため、所得税が非課税でも住民税が課税されるケースが生じ得ます。
なお、住民税の課税は令和8年度(令和7年中の所得に基づく)から適用されます。
〈106万円の壁〉社会保険
「106万円の壁」とは、以下のすべての要件を満たした場合に、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務づけられるラインです。
- 従業員数51人以上の企業に勤務
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(年収約106 万円)
- 継続して2か月を超えて雇用される見込みがある
- 学生でないこと(※夜間・通信制・定時制の学生は原則として加入対象外)
なお、この制度は、今後3年以内に企業規模や賃金要件の撤廃を含む更なる拡大が予定されています。
〈123万円の壁〉所得税(扶養控除)
「123万円の壁」とは、扶養控除の適用を受けるために扶養される家族の給与収入が123万円以下である必要があることを指します。扶養親族の所得要件が58万円に引き上げられ、給料所得控除の65万円と併せた123万円が扶養者でいる条件となります。これは令和7年度の改正で、それまでの「103万円の壁」が引き上げられたことによる変更です。
〈130万円の壁〉社会保険(扶養認定)
「130万円の壁」とは、被扶養者として健康保険に加入し続けられる給与収入の上限です。これを超えると、自ら国民健康保険または勤務先の社会保険に加入する必要があります。実際の認定は「年収130万円未満かつ恒常的な収入であること」を基準として、各健康保険組合や協会けんぽで判断されます。
一方で、令和7年度の改正では、19歳以上23歳未満の扶養親族に対して「特定親族特別控除」が創設され、扶養控除の対象となる給与収入の上限が150万円まで拡大されました。ただし、この社会保険上の扶養の基準は変更されていないため、130万円を超えると扶養から外れる可能性があり注意が必要です。
〈160万円の壁〉所得税(非課税ライン)
「160万円の壁」は、給与所得のみを得ている人が所得税を負担せずに済む年収の上限を示しています。令和7年度税制改正により、年収200万円以下(合計所得132万円以下)の人に対して基礎控除が従来の48万円から95万円に引き上げられ、また給与所得控除も最低65万円に引き上げられました。
この結果、給与収入が160 万円以下であれば、
給与収入 − 給与所得控除(65万円) − 基礎控除(95万円)≦ 0円
となり、課税所得がゼロになるため所得税が課されません。
(※給与所得のみで、他に所得がないことが前提)
以上のとおり、所得税制度が改正されて減税となる一方で住民税や社会保険制度の仕組みは依然として現行制度が維持されているため、思わぬ「手取りの逆転現象」や加入義務の発生などに注意が必要です。
また、「年収の壁」制度は今後も段階的に見直されていく可能性が高いため、最新の制度動向を注視していく必要があります。
参考資料
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
- 財務省「令和7年度税制改正大綱」
- 厚生労働省「社会保険の適用拡大について」